シリーズ『魔狼群影』 1.ネイチャー・ガール
このショートストーリーでは、登場人物・組織設定など、小説「死の先に在るモノ」を未読の方には分からない要素が存在します。
よって、「死の先に在るモノ」を未読の方は、面白さが半減する可能性があります。
ぜひ、「死の先に在るモノ」(少なくとも第5話まで)を先にご覧になった後で、お楽しみください。
また、本作品に登場する「イタチのアズマ」と「蠍のクリムゾン」のプロフィールを事前にチェックされることをオススメします。
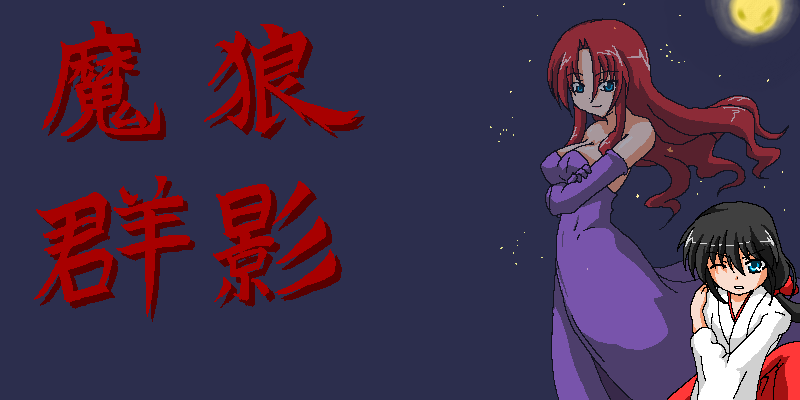
一の巻 鵠、無垢なる鼬の仔を託され、往きて蠍の助力を冀ふ
ある日、白鳥のセリーナはフェンリル本部内の自分のとは違うオフィス内にいた。
ソファにかけたセリーナの前に座っているこの部屋の主である人物も、セリーナとほぼ同年代の女性である。170半ばを超える長身で抜群のプロポーションの上に、燃えるような赤い色の髪と濃い青の瞳が絵に描いたようなコントラストをなすという、一言で言えば、えらく派手な美人だった。
チーム『プアゾン』のリーダー――クリムこと蠍のクリムゾンである。
「で? 何のご用? わざわざお運びのわけは」
コーヒーを勧めながら、用件を尋ねてきた相手にセリーナは礼を言って、答えた。
「あなたに、ちょっとお願いがあって・・・」
「お願い?」
「ええ。今、わたくしが戦闘訓練を任されている、イタチのアズマという・・・そう言えば、たしかあなたにも、一度紹介したことがあったわよね?」
「ああ・・・例の、天神会から司令がムリヤリかっさらって連れてきたとかいう・・・」
「そうそう」
通常ならかなり不穏当なはずのクリムの台詞にも、セリーナは軽く応じた。そういうことを気にしないですむ場所であり、そのくらいの彼女たちの間柄でもある。
「覚えてるわ。何だか、お人形みたいな子だった・・・」
――さすが・・・。
その『お人形』という言葉に含まれた、『きれい』とか『かわいい』とか以外のニュアンスを感じ、セリーナは会心の思いを得た。
クリムは非常に鋭い洞察力の持ち主だった。一度会った、あの時の印象だけで、すでにアズマという娘の本質的なものを見抜いたものだろう。
そして、これなら頼める、との意を強くする。
「実は、その子の訓練の件であなたに協力してほしいの」
「あなたにそういうことを頼まれるのは、これで二度目ね」
数年前、セリーナは、当時やはり教官役を務めていた白鷺のサキという少女の戦闘訓練の一環として、経験を積ませるため、クリムたち『プアゾン』に模擬戦の相手を依頼してきたことがあったのだ。
「いえ、あの時とは違って、模擬戦の相手というより・・・」
「・・・?」
視線で説明を促すクリムに、セリーナはイタチのアズマという娘について、訓練を開始した頃からの話を始めた。
「そもそも最初は、普通の運動すらろくにしてこなかったみたいで、すこし走らせただけでも倒れるわ、筋力もぜんぜんないわで、途方に暮れたくらいだったんだけど――腹筋をやらせたら、いちどもできなかったんで、本人は上体を起こそうと必死に力を入れているんだけど、はたから見ると、ただずっとあお向けに寝てるようにしか見えなかったりとか・・・笑い話じゃないのよ? でも、そっちの方は地道なトレーニングをくり返すことで、どうにかまともになってきたわ。――でも、そうやって、ようやく基礎体力がついてきたところで、いよいよ戦闘訓練をはじめてみたら、これが・・・」
「どうしたの?」
「てんで、ダメなのよ。とてもとても、サキを教えていたときのようなわけにはいかないわ」
「サキと比べることじたい、間違いだとおもうけどね。彼女は、特別だし」
「それはよくわかってるわ。わたくしも、そこまで望んではいない――でも、それにしてもね・・・根本的に、戦闘のセンスというものに欠けてる気がする」
「・・・それは、要するに、戦いに向いてないってことよね」
「そう――あ、いえ、でも、覚えは悪くないし、一度覚えたことは忘れないのよ」
「? なら、センスないわけでもないんじゃ・・・?」
「いえ、でもね・・・応用がきかないの――それはもう、おどろくくらい」
「どんなふうに?」
「すでに知っている状況だったら、対応できる。その通り、正確にまちがいなく。でも、その経験を生かして、別の新しい状況に対処することはできないの。別とはいっても、普通なら、それまで身につけたものを使って、予測を立ててなんとか工夫できそうなことでも、あの子だと、まずムリ」
「・・・それは何? 記憶と感情を喪ったとかいう、その子の精神的なものがやっぱり影響しているわけ?」
「そうだと思うわ。正確なところは、わたくしにはわからないけど」
「・・・」
「仕方がないから、こういうような場合には、このように対処するという、いくつものパターンに分けて、それを覚え込ませて、そのうえで個々のいろいろな状況をそのいずれかに当てはめて、それにそって行動する、という感じで教えて、今まで訓練してきたの。――でも、そのパターンと相違点があると、どうしていいか、わからなくなる。少し違っていると、もうだめ。だから、その覚えさせなければならないパターンの多いこと多いこと・・・」
「なるほどね・・・それは、たいへんそうだわ」
クリムはコーヒーを少し口に運んでから、考えをまとめるように、
「話を聞いていると、そういう子は、やっばり戦闘には向かない・・・少なくとも、最前線で戦わせるべきではないと思うけど。味方の掩護・支援とかの役をするというなら、まだわかるわ。いえむしろ、その方がその子の力を引き出すことになるんじゃない?
適材適所ということがあるでしょう。その子には、たとえばサキのようなすぐれた戦闘勘があるわけじゃない。でも、別の分野では、また他の誰にもない力があるわけでしょう。稀代の巫女とか聞いたわよ。その霊力を有効に使うには・・・」
「・・・そうもいかないの」
クリムの言葉をセリーナは途中で遮ったが、力のない様子だった。
「セリーナ。こんなこと、今さらあなたにいうことでもないけど・・・戦いなんて、イレギュラーの連続よ? 何が起こるかわからない。仮に、似たような状況に見えたとしても、ほんとにまったく同じなんてことはあり得ないし・・・臨機応変の対処のできないような者に、前線での戦闘は無理だわ」
「あの子を前線に出すというのは、もう決定事項なの。それが前提なのよ」
セリーナは繰り返した。だが言外には、自分も本当には賛成ではないという意をにじませて。
「そう――またぞろ、上からのお達しなわけね」
クリムは肩をすくめた。それ以上、もう言うことはせずに、
「それで? わたしは、何をすればいいの」
「あなたの言うとおり、パターンで、すべての戦いに対応させるのはむずかしい――それでも、こちらが攻撃をしかける側で、あの子が自分のペースで攻められれば、まだ何とかなると思うの。それなら、ある程度は、状況もこちらで設定できるはずだし。あらかじめ、それぞれの場合にふさわしいやり方を叩き込んでおけば――それにわずかずつではあるけれど、少しは応用も利くようになってきたようにも見えるし・・・。
でも、防御となるとね・・・一方的に攻めきってことが済めばいいけど、いったん受けに回ると、あの子はどうもだめなの。どんな反撃が来るか、すべて予想をつけることはできないというのもあるけど・・・それよりまず、あの子には危険に対する意識が薄い気がする。攻撃を避けよう防ごうとする必死さがもうひとつ感じられない。不真面目とかいうわけではないのよ。でも、本人にどこか現実味がないようなの」
う~ん・・・クリムは少し唸ってから、
「それは・・・こわいと思う気持ちもないから?」
「ええ、おそらくは・・・。」
「そうなると、深刻ね。防御の重要さはいうまでもないわけだけど、通常だれに教えられるまでもなくわかっている、それを重視する大きな動機のひとつがその子にはないということだから」
セリーナはうなずいて、
「それで、あなたにお願いしたいのは、根本的な身を守る感覚みたいなものをあの子に身につけさせる方法が何かないか、考えてほしいということなのよ。――具体的な方法でなくても、何かヒントだけでももらえれば、とても助かるの・・・一度、あの子を見てもらえないかしら?
わたくしもずっと考えてきたんだけど、とくにいいアイディアもなくて、正直、ほとほと困ってるの。わたくしとしては、わたくしとはまた別の新鮮な目であの子を見てくれる人がほしいわけなの」
「わかったわ。ご期待に添えるかわからないけど、一度会ってみましょう」
「ありがとう。恩に着るわ――それで、いつ?」
「早いほうがいいわね・・・そうね、今日でもいいけど、夜にはあくんだけど、その前、夕方ぐらいに少し行かなきゃならないところがあって・・・」
「どこ?」
クリムは、緩衝地帯の、とある建物の名を口にして、
「役所の世界の各機関の親睦を深めるためっていうパーティがそこであるんだけど・・・それに出席しないといけないのよ。――もちろん、表向きの天界裁判所の職員としてだけどね」
ああ、そういうのにはいかにも狩り出されそうね、この人は・・・とセリーナは反射的に一瞬納得してから、すぐまた、いや、でも、天界裁判所の職員としては派手すぎるんじゃ・・・? と思いなおした。むろん、どちらも口に出したりはしない。
「でも、そうね――わたしは少し顔を出しさえすればいいから、そのあとで・・・よかったら、そこで落ちあいましょうか?」
「いえ、ごめんなさい。わたくしも、その時間には用があって・・・でも、そうか、アズマだけ行かせてみてもいいのか・・・あの子も、少しはそういう場にでてみるのも、いい社会勉強にもなるかもしれないし――あー、だけど、あの子1人だけっていうのは、やっぱり・・・」
「世間知らずといったって、子どもじゃなし、だいじょうぶでしょ? それに、すぐわたしと一緒になるはずだし、公式なパーティだから、めったなことは・・・」
「そうね。地図を持たせて、場所もよく言って聞かせれば、きっとだいじょうぶよね。――1人でも、迷子になったりは・・・」
「――いえ、そういう意味じゃ・・・って? というか、そういうことまで、心配しなきゃならない子なの?」